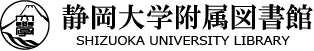スコットランドの首都グラスゴーは予想に反して最高気温が20度に達するほどの暖かい春でした。英国では黒いオースチンがお決まりのタクシーですが(それ以外のもありますよ)話し好きの運転手ジョンは二十数年ぶりの記録更新だと上機嫌。記録って、でもどんどん書き換えられるものだよね、とも付け加えて。夏はどうなの、と聞いたら、こんなものかな、と。後ろ向きになって熱心にしゃべるので私は前の車との距離が気になりましたが、そこはプロ。街では、さきの週末に夏時間が導入され、イースターも近づいて人々は太陽を思う存分楽しむように、まだ陽の高い公園で思い思いに午後の時聞を楽しんでいました。水曜の午後のことです。さて、年度を締めくくる卒業論文や修士論文などの審査を終えて一区切りした3月の下旬にスコットランドへやってきたのは英国の電子学術情報に関連して図書館と出版社が情報や意見を交換するUKSGという会議に出席するのが目的でした。iPadやKindleの登場とともに本の電子化が急速に進んでいますが、少し遅れて日本でも書籍の電子化の動きが活発になりそうですね。この原稿を書いているロンドンからの帰りの機内で読んだ朝日新聞の電子版の一面にも、政府が遅れている日本語の書籍の電子化に150億円を投入するという記事が出ていました。これに対して世界が舞台の研究分野の学術情報はいっそう速い速度で電子化が進んでいます。27カ国から840人が参加した (残念ながら日本からの参加は多分私一人でした) 2012年のこの会議の議論では、学術情報とそれを扱う大学などの研究機関の図書館のあり方が対象でしたが、それ以外の図書館についても同じだなと思われることがいくつもありました。
図書館ということで私が興味深かったのは、ダブリンの公立病院の日本流に言うなら上級司書にあたる方が、25%もの図書費のカットにどのように対応したか、講演されていたことです。この分野の世界をリードする会議で大学や研究機関にまじって公立病院の司書の方が現場の話をする。その、全体を包括しようとする会議の姿勢に感心しました。得てして縦割り行政を投影してか分野別での会議やシンポジウムはあっても大くくりにすることがどうも我が国では少ないな、と。
さて電子化の話、に入る前にもうひとつ。今回の英国出張で私ははじめて大英図書館に足を運ぶことができました。館内もそうですが、ギャラリーはとりわけ圧巻でした。ダビンチの手稿や、オスカーワイルドの本への書き込みや、あふれるほどの展示の中でもぜひ見てみたかったのは13世紀はじめ、貴族たちが国王ジョンに飲ませた要求をしたためたマグナカルタ。本物、です。きれいで几帳面なペン文字で書かれた2、3千 (?) の一枚の紙は、この国の最も重要な、そしておそらく最古の公文書としてギャラリーの特別室に展示されていました。説明文には、この文書には何の拘束力もないが…。と書かれています。貴族たちが国王の執政を認める上で言うべきことを文書にした、ということでしょう。言うべきことをことばにする。それを文書にして残す。文書や書籍の保存 (アーカイビング) の基本がここにあるように素人館長である私はすっかり納得させられました。翻って我が国の古い古文書は、思い出すことができるご朱印状にしても用件だけをしたためた簡単なものでしたね。歴史を知る上では重要であっても、そこから当時の人々はなかなか見えにくい。この、語ること、書くことの歴史の違いは、図書館というものを考える上でもかなり重要だなと感じています。
さて電子化。もう紙数がなくなってきましたので、会議のトップの基調講演で、カナダ人のベテラン、スティーブ・アービスさんが指摘したことを紹介して終わりにします。図書館の司書の仕事に触れての内容でした。「人は質問します」「人は何でも聞きたがります」「自分のために」…。何を答えるか、どのように答えるか、そこのところが大事ですが、答えの先にあるのは、人と人がつくりだす “社会Society” です、と。私たちも、大学図書館の立場を少し踏み出して “Society” の中での図書館として、という視点をたまには持ってみませんか?